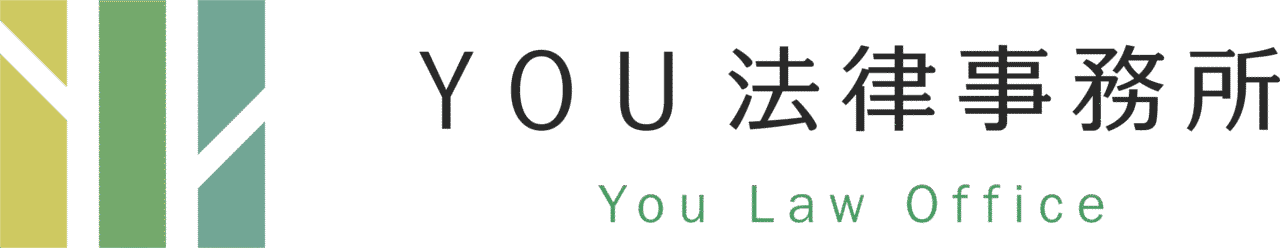Knowledge基礎知識
離婚時の親権はどう決まる?決め方のポイントをわかりやすく解説
離婚を考える場合、子どもがいる夫婦にとって避けて通れないのが「親権」の問題です。
誰が子どもを育てるのか、どのように決めるのかを理解しておく必要があります。
今回は、親権の基本的な考え方と、決め方についてわかりやすく解説します。
親権とは
親権とは、未成年の子どもに対して、法律上の責任を持つ権利・義務であり、大きくは子の監護権と子の財産管理権であるといわれています。
民法第818条第3項によれば、婚姻している夫婦は、共同して親権を行使するとされています。
しかし、離婚などの事情でどちらかが親権を行使できない場合は、もう一方が親権を持ちます。
日本では、離婚後の親権は父母どちらか一方のみが持つ「単独親権」が原則です。
夫婦が協力して子どもを育てる「共同親権」は、現行制度では認められていません。
なお、日本においては、「離婚後の共同親権」を導入する改正民法が2024年5月に成立し、2026年5月までに施行される予定となっています。
ただし、現時点では、まだ共同親権制度は施行されていないため、現時点では、離婚後の親権は父母のどちらが親権を持つかを決める必要があります。
親権の決め方
親権の決め方は、離婚の方法によって異なります。
協議離婚の場合
協議離婚の場合は、夫婦で話し合い、どちらが親権を持つかを合意して決めます。
子どもの進学や病院のこと、お金の管理などについて、「どちらの親が決めるのが子どもにとって良いのか」を考えながら話し合います。
親権者を記載していない離婚届は受理されません。
つまり、親権の決定は、離婚成立の必須条件ともいえます。
当事者間の協議で話し合いがまとまらない場合
当事者間で親権についての合意ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停においても、裁判所が子どもの利益を最優先に考えて、どちらが親権を持つべきかを話し合います。
調停で合意ができない場合には、離婚訴訟を提起し、最終的には裁判所が下記の観点に照らして総合的に判断し、親権者を指定します。
親権を判断する基準
家庭裁判所では、以下のような観点から総合的に判断されます。
以下の判断基準は、あくまでも一般論であり、家庭裁判所は、各家庭の個別事情に照らして、子の意向やこれまでの係争状況を踏まえて、親権者を総合的に判断します。
| 基準 | 説明 |
| 主たる監護者 | 普段から子どもの面倒をどちらが主に見ているかが重視されます。日ごろから子どもと多くの時間を過ごしていた親が、親権を得やすいとされています |
| 子どもとの愛着関係 | 子どもが安心して甘えられる相手か、信頼関係ができているかも重要です。親がどれだけ子どもに関心を持ち、愛情を注いでいるか、また子どもがどちらの親に心を開いているかなどが考慮されます |
| 兄弟姉妹の一体性 | 兄弟や姉妹がいる場合は、なるべく同じ親のもとで一緒に生活できるようにするのが望ましいとされています。兄弟姉妹を引き離すことは、子どもにとって精神的な負担になる可能性があるためです |
| 生活環境・経済力 | 生活の安定も判断基準になります。収入や仕事の状況なども見られますが、経済力だけで親権が決まるわけではありません。また、病気なども考慮されますが、育児ができる程度であれば親権者になることは可能です |
まとめ
親権は、離婚時に必ず決めなければならない大切な要素です。
話し合いで決められるのが理想ですが、まとまらない場合は家庭裁判所で判断されます。
親権について不安がある場合は、早めに弁護士などの専門家に相談すると安心です。