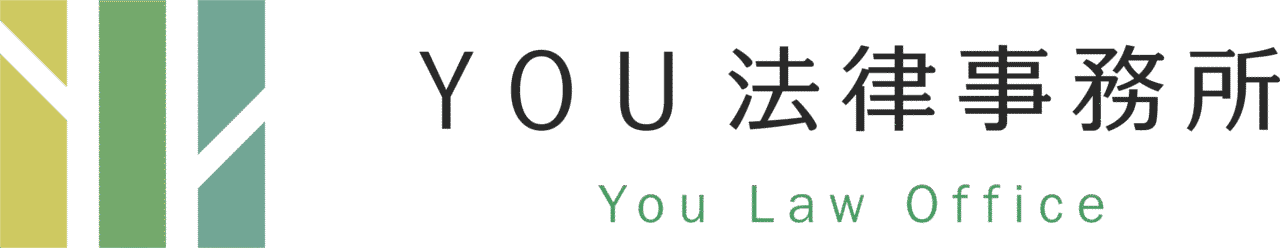Knowledge基礎知識
相続の手続きはどうするべき?進め方を5つのステップで解説
家族が亡くなった際、遺産を引き継ぐには「相続の手続き」が必要です。
しかし、いざ自分が行う立場になると「何から始めるべきかわからない」という方も多いかもしれません。
今回は、相続の基本的な流れと注意しておきたいポイントを解説します。
また、今回は、被相続人(お亡くなりになった人)が遺言書を残していなかったケースで解説いたします。
遺言書がある場合には、遺言書の記載内容が優先され、相続人間での遺産分割協議は不要となります(ただし、相続人全員が遺言書に合意しない場合には、遺産分割協議が必要なる場合もあります)。
相続手続きの大まかな流れ
相続手続きの大まかな流れは、以下の5つのステップです。
①死亡届の提出・葬儀の実施
②相続人の確認
③相続財産の調査
④相続の方法の選択
⑤遺産分割協議・各種名義変更
それぞれ確認していきましょう。
①死亡届の提出・葬儀の実施
まずは市区町村役場に死亡届を提出します。
同時に火葬許可証の取得や、葬儀の準備も行います。
この段階では、まだ相続の具体的な話は進みません。
②相続人の確認
次に行うのは、誰が法定相続人になるのかの確認です。
戸籍謄本を取り寄せ、配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹など、相続人の範囲を正確に調べます。
確認によって得た情報は、その後の遺産分割や各種手続きの基礎になります。
③相続財産の調査
被相続人の財産や借金の内容を調べます。
調査対象には以下のようなものがあります。
- 預貯金や不動産
- 株式や保険
- 借金やローンなどの負債
普段から管理している財産であれば特定しやすいですが、暗号資産など把握しにくいものもいくつかあるため、注意が必要です。
財産を特定できたら、プラスの財産とマイナスの財産をすべて洗い出し、相続するか放棄するかの判断をします。
④相続の方法の選択
財産の内容がわかったら、相続の方法を選びます。
主に以下の3つがあります。
- 単純承認:すべての財産と負債を引き継ぐ
- 相続放棄:何も相続しない(家庭裁判所に申述)
- 限定承認:プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ
なお、相続放棄や限定承認には「相続開始を知ってから3か月以内」という期限があるため、早めの判断が必要です。
⑤遺産分割協議・各種名義変更
遺産分割協議では、相続人全員で話し合い、財産をどのように分けるかを決めます。
合意できたら、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更や預金の引き出しなどを行います。
名義変更は、手間がかかる場合も多いため注意してください。
たとえば被相続人が何社にも分けて預金を管理していた場合、金融機関ごとに手続きをしなければなりません。
なお、相続税の申告が必要な場合は、被相続人の死亡日(厳密には、死亡したことを知った日)から10か月以内に税務署へ申告・納付が必要です。
まとめ
相続手続きは、段階ごとに必要な作業が決まっており、期限が設定されているものもあります。
大切なのは、早めに全体の流れを把握して動くことです。
不安な点があれば、弁護士などの専門家の力を借りて、円滑に進めましょう。