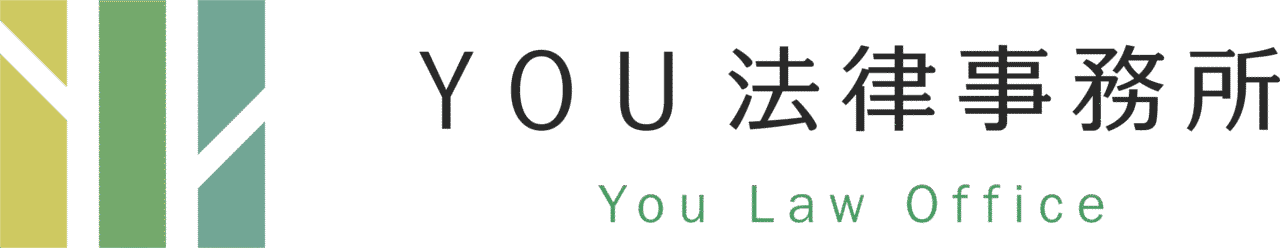Knowledge基礎知識
自筆証書遺言の書き方とは?基本ルールと注意点をわかりやすく解説
「自分が亡くなったあと、家族に迷惑をかけたくない」と思ったら、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書のうち、自分で書いて残せる「自筆証書遺言」は、費用もかからず手軽に作成できます。
今回は、自筆証書遺言の基本的な書き方や注意点をわかりやすく解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を手書きで作成する遺言書です。
公証役場を使わないため、手軽に作成しやすいというメリットがあります。
ただし、書き方を間違えると無効になるリスクがあるため注意が必要です。
遺言書保管制度について
自筆証書遺言は、以前は自宅で保管するのが一般的でしたが、現在は法務局で保管してもらえる制度があります。
紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認が不要になるなど、多くのメリットがあります。
ただし保管の申し込みは、本人が法務局に出向いて行かなければなりません。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言が有効と認められるには、民法で定められた形式を守る必要があります。
主なルールは以下の通りです。
- 全文を自分で手書きする
- 日付・署名・押印をする
- 訂正には特別な方法を用いる
それぞれ確認していきましょう。
全文を自分で手書きする
民法第968条第1項によれば、遺言の内容はすべて本人の手書きである必要があります。
PCでの作成や代筆は認められていません。
ただし、財産目録(預金口座や不動産の明細など)については、平成31年(2019年)1月13日以降、PC作成の添付が可能になりました。
日付・署名・押印をする
遺言書には、作成した日付を明記し、自分の名前を書いて印鑑を押す必要があります。
日付は「令和〇年〇月〇日」と具体的に記載してください。
「吉日」など、あいまいな表現は無効になるリスクがあります。
訂正には特別な方法を用いる
一度書いた遺言書の内容を訂正する場合は、訂正箇所に印を押し、訂正内容を明記するなどのルールがあります(民法第968条第3項)。
訂正方法が正しくないと、その部分が無効になる可能性があります。
自筆証書遺言を書く際の注意点
内容はできるだけ具体的に書いてください。
「長男にすべて任せる」などのあいまいな表現では、相続人の間でトラブルになる可能性があります。
誰に、どの財産を、どのように渡すのかを明確化するのが重要です。
また、遺言書を書いてから、家族構成や財産の内容が変わるケースもあります。
古い内容のままだと、意図しない相続になるかもしれません。
一度書いて終わりではなく、数年おきに見直すのがおすすめです。
まとめ
自筆証書遺言は、費用をかけずに自分で作成できる手軽な方法ですが、形式を守らないと無効になる可能性もあります。
書き方や保管の方法にも注意しながら、大切な家族のために準備を進めましょう。
不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談しながら作成すると安心です。